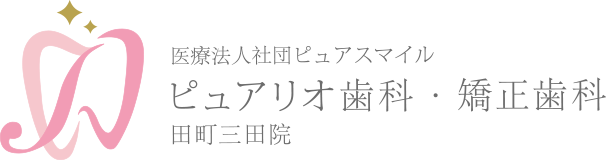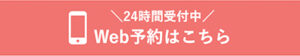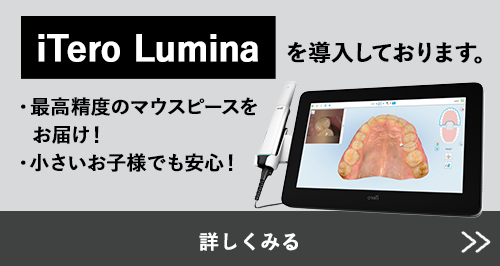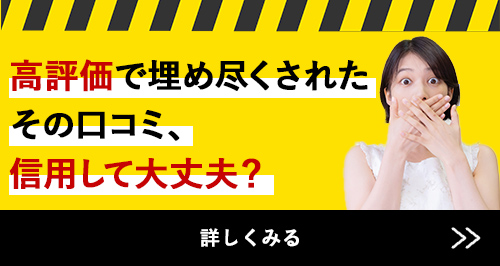こんにちは。
ピュアリオ歯科・矯正歯科スタッフです。
マウスピース矯正(インビザライン※)は、透明で目立たないことや、一般的なワイヤー矯正に比べて痛みが少ないことで人気の矯正治療です。
マウスピース矯正をお考えの方のなかには、マウスピース矯正中の食事について、痛くないのか、気をつけることはないのか等、気になっていらっしゃる方も多いと思います。
そこで今回は、マウスピース矯正中の食事の痛みについてや飲み物、外食や飲み会で気をつけること等をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
マウスピース矯正(インビザライン)中の食事は痛い?
「矯正中の食事は痛そう」というイメージをお持ちの方は多いと思いますが、実際には、マウスピース矯正では食事中に痛みを伴うことはほとんどありません。
マウスピース矯正とワイヤー矯正の大きな違いのひとつが、マウスピース矯正は、飲食の際は装置を外して思いきり食事を楽しめる、という点です。
ワイヤー矯正は、自分で取り外しができないため、食事中もずっと装置を着けたまま。そのため、特に月に1度のワイヤー交換後の1週間前後は、食べ物を噛むたびに痛みがあります。激痛を感じるという方も少なくありません。お豆腐やヨーグルトなど、やわらかいものだけを食べて過ごされる方もいらっしゃるほどです。
また、ワイヤー矯正の場合、装置に食べ物が引っかかるので、人との食事中にずっと気になってしまったり、食後の歯磨きやお手入れにもとても時間がかかったりと、痛み以外にも食事で不便を感じることがいくつもあります。
一方、マウスピース矯正は、自分でマウスピースの取り外しができ、食事のときには必ず外します。そのため、食べ物を噛むときにワイヤー矯正のような痛みはなく、食べ物が装置に引っかかってしまう心配もほとんどありません。
ただ、おせんべいやりんごなどの固いものを食べたときには、歯の根っこのあたりにズキズキとした痛みを感じる方も中にはいらっしゃいます。
(これには個人差があり、この記事を書いている私もマウスピース矯正中ですが、固いものを食べて痛みを感じたことはありません)
ちなみに、マウスピースは1日20時間以上着ける必要があります。そう聞くと、「大変そうだな…」と思われるかもしれませんが、朝・昼・晩の3食、さらに間食と、それぞれゆっくり1時間ずつ食事の時間をとっても20時間は確保できますので、「意外と余裕で20時間以上着けられた」という方がほとんどです。
ワイヤー矯正に比べて、食事についての制限やストレスがとても少ないところがマウスピース矯正の大きなメリットなのです!
マウスピース矯正(インビザライン)中の食事で痛みを感じる理由
先述した通り、マウスピース矯正中の食事で痛みを感じることはほとんどありません。ただ、おせんべいやりんごなどの固いものを食べたときには、歯の根っこのあたりにズキズキとした痛みを感じる方も中にはいらっしゃいます。
(これには個人差があり、この記事を書いている私もマウスピース矯正中ですが、固いものを食べて痛みを感じたことはありません)
では、なぜ固いものを食べると痛みを感じることがあるのでしょうか?
それは、歯がしっかりと動いているからこそなのです。
歯は通常、少し押したぐらいでは動きませんよね。歯は通常、あごの骨の中にしっかりと埋まって、固定されているためです。
そこへマウスピースを装着することによって、歯を動かせるほどの力がかかります。すると、歯の根っこの周りにある歯根膜といわれる部分が、力がかかっているほうの骨を少しずつ溶かし、反対側に骨を形成していきます。この骨が溶けるときに、歯根膜から痛みを感じさせる物質が分泌されます。その状態で固いものを食べると、歯の根っこにズキズキと痛むことがあるのです。
そのため、固いものを食べたときの痛みは、歯が動いている証拠ともいえます。理想の歯並びに近づいているしるしですので、自分が痛みを感じる食べ物だけを避けて、上手く付き合いながら乗り切っていけば問題ありません。
マウスピース矯正(インビザライン)中に飲み物はマウスピースを着けたまま飲んでも大丈夫?
マウスピースを着けたままの食事はNGですが、飲み物なら、着けたまま飲んでも問題ありません。ただ、マウスピースを着けているときは、砂糖が含まれている飲み物や、色のついた飲み物は、基本的にNG。水や炭酸水、白湯にしておきましょう。
理由は、歯とマウスピースの間に糖質が入り込んで虫歯の原因となったり、マウスピースや歯、アタッチメント(マウスピース矯正中に歯の表面に付ける白い装置)が着色したりしてしまうためです。
また、熱い飲み物もマウスピースの変形の原因となりますので、マウスピースを着けているときには避けましょう。マウスピースの耐熱温度を考えると、60℃以上の飲み物は避けた方が安心です。
マウスピースを着けたまま飲んでもOKな飲み物
- 水
- 炭酸水
- 白湯
マウスピースを着けたまま飲むのはNGな飲み物
- 砂糖が含まれた飲み物
- 色のついた飲み物(特にコーヒー・紅茶・赤ワインなどは着色の原因になりやすいです)
- 熱い飲み物(60℃以上)
とはいえ、外出先で急きょ飲み物を出してもらった場合など、どうしてもマウスピースを外せるタイミングがないこともあると思います。そんなときは、その場ではマウスピースを着けたまま飲むことになっても、その後なるべく早くマウスピースを外して歯磨きをするか、歯磨きが難しいときはせめて口をゆすいで、しっかりとアフターケアができれば大丈夫です!
マウスピース矯正中の外食・飲み会で気をつけること
マウスピース矯正では、1日20時間以上マウスピースを着けている必要があります。
ただ、外食や飲み会など、人との食事の席は時間が長くなることも多いですよね。そんなときは、そこまで頻繁でなければ(週に2~3回程度)、外して思い切り楽しんでも大丈夫です。
ただ、下記の3点にだけは気をつけるようにしてください。
外している時間をなるべく短くする
外食や飲み会のときは外して楽しんでもOKですが、外している時間をなるべく短くすることがとても大事です。外している時間があまりに長いと、歯が治療計画の通りに動かなくなり、マウスピースのつくり直しが必要になったり、治療期間が延びたりしてしまうからです。
たとえば、外食や飲み会のときには、家を出るときにマウスピースを外すよりも、お店についてからマウスピースを外す。また、食事のあとも、家に帰ってからマウスピースを着けるよりも、お店でマウスピースを着けてから帰った方がより長い時間着けていられます。
行き帰りの時間だけでも、装着時間が数時間変わってしまうこともあるので、できるだけ食事の直前に外し、直後に着け直すことを徹底しましょう。
食後のケアに気をつける
外食や飲み会の後にマウスピースを着け直す際は、必ず歯磨きをしてお口の中を清潔にしてからにしましょう。歯のすき間や表面に食べカスや飲み物が残ったままマウスピースを着けると、虫歯や着色の原因になってしまうからです。
そうは言っても、外出先では歯磨きがどうしても難しい場合もありますよね。そんなときは、せめてお水かマウスウォッシュで口をゆすいでからマウスピースを着け、家に帰ったらしっかり歯磨きするようにしてください。
(私はそんなときのために、ミニサイズのマウスウォッシュを持ち歩いています)
マウスピースは必ず専用ケースに入れる
取り外したマウスピースは、必ず専用のケースに保管しましょう。適当に取り扱ってしまうと、マウスピースの破損や紛失につながってしまいます。
よくあるのは、ついそのままポケットに入れて壊れてしまった、ティッシュやペーパータオルに包んでおいたらゴミと間違えて捨ててしまった、お店に忘れてしまった…などです。
特にお酒の席では、マウスピースの取り扱いが適当になりがちです。酔ってしまう前に、必ず専用ケースに入れてバッグに入れてしまいましょう!
マウスピース矯正(インビザライン)中の食事で気をつけること。まとめ
マウスピース矯正は、装置を外して食事を思い切り楽しめることがワイヤー矯正との大きな違いであり、メリットです。いくつかの注意点だけしっかり守っていれば、外食や飲み会も楽しみながら治療できます。無理なくがんばっていきましょう♪
監修歯科医師

医療法人社団ピュアスマイル 理事長 湊寛明
経歴
私立 広島学院高等学校卒業 国立 九州大学歯学部卒業・歯学学位取得 九州大学病院研修医 終了 埼玉県 オレンジ歯科クリニック 栃木県 丹野歯科医院 山口県 みなと歯科医院 副院長 大手矯正歯科グループ 院長 ピュアリオ歯科・矯正歯科 田町三田院 設立 医療法人社団ピュアスマイル設立、理事長就任
ご挨拶
誰もが憧れる白くて美しい歯で、個人の魅力を最大限に引き出し、 一生涯、歯の疾患で歯を一本も失うことのない未来を創る。

歯の見た目の美しさはもちろん、人が一生涯、長期的かつ健康に機能できるものとなるように、かみ合わせも力学的に良好な治療を考え、総合的な歯科の知識と予防的な概念で治療をしていくのが本当の矯正・矯正歯科治療です。 歯科治療は医療の中でも、医師の考え方や感性・技術、医院の設備によって結果が大きく変わる業界です。 既に神経の治療がされていたり、見た目や適合の悪い大きな被せものが入っていれば話は別ですが、美しさを手に入れるためだけに必要以上に健康な歯を削り、神経を取ってまで無理やりセラミックの被せものをする必要はありません。 患者さまの望む最大の効果を合理的で正しい考え方と治療方法で結果を出すとともに、生涯歯の健康を維持しそこから全身の健康につなげていただけることが何より大切だと思っています。 患者さまのお悩みやご要望をお聞きし、最善の結果となるよう治療をご提案いたします。